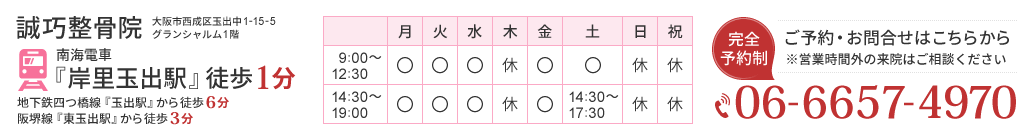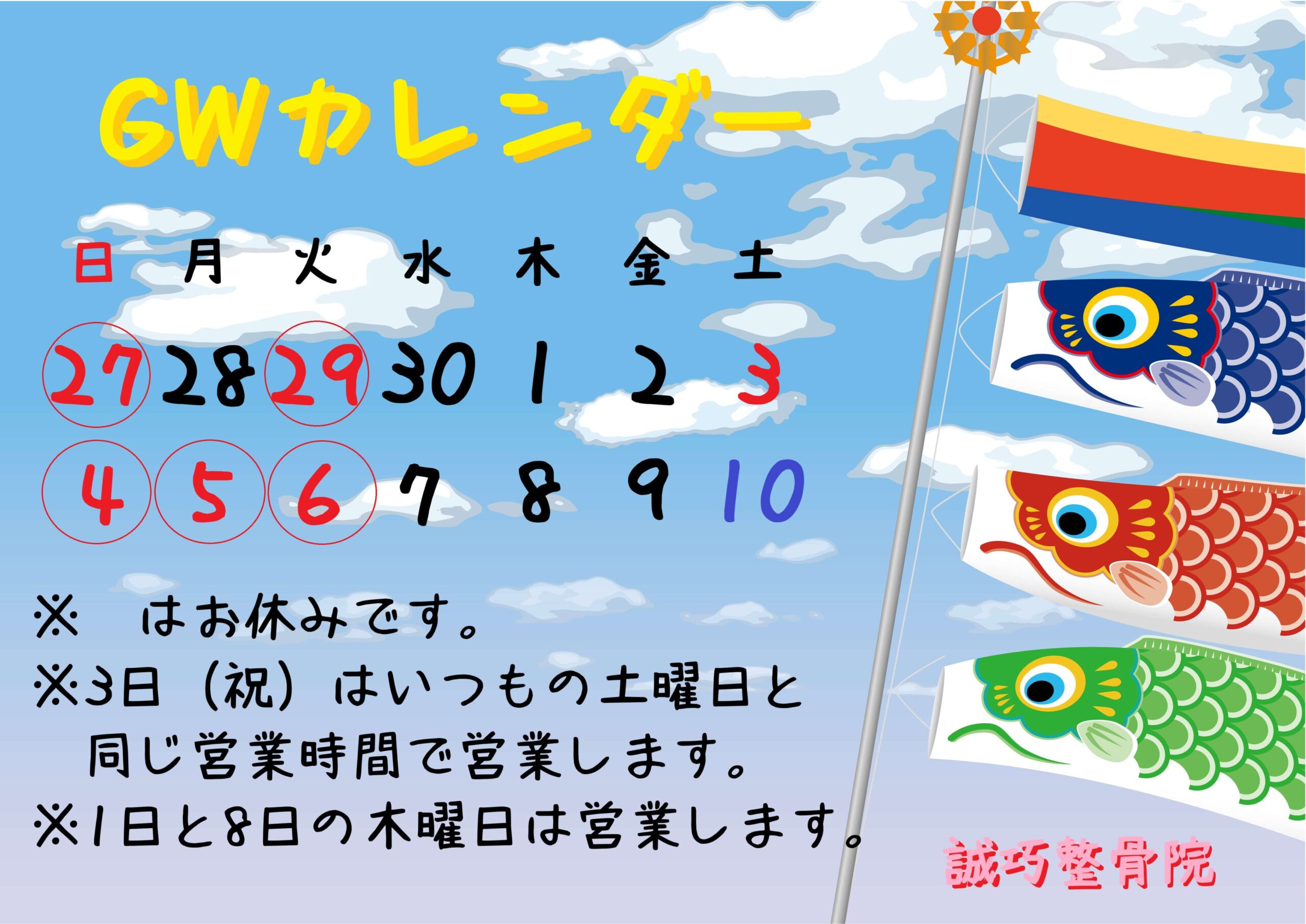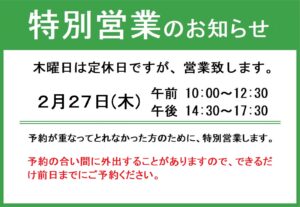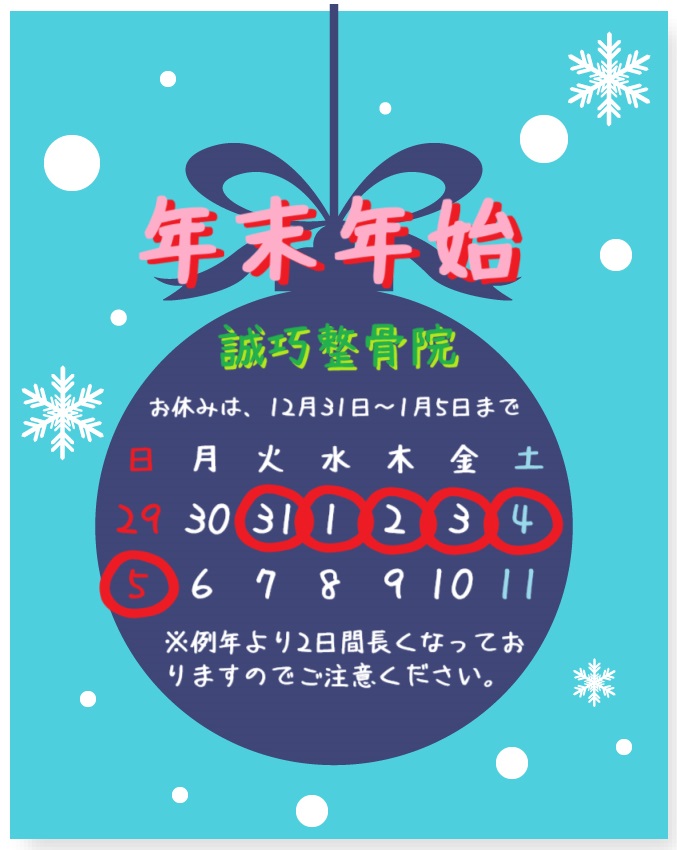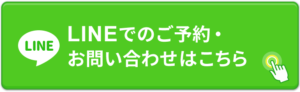頭痛・肩こりが治らない原因は「セロトニン不足」かもしれません
〜薬やマッサージで良くならない方へ、根本改善のヒント〜
「マッサージを受けてもすぐに肩こりが戻る」「頭痛薬を飲んでも根本的に改善しない」そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
実は、慢性的な頭痛や肩こりの背景には「セロトニン不足」が関係している可能性があります。
今回は、セロトニンと頭痛・肩こりの深い関係について詳しく解説いたします。
目 次

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質で、私たちの心と体の健康に欠かせない重要な成分です。
セロトニンの主な働き
・精神の安定:不安やイライラを抑制
・睡眠の質向上:メラトニンの原料となり、良質な睡眠をサポート
・痛みの調節:痛みを感じる感度を調整
・血管の収縮・拡張調節:頭痛の発生に深く関与
特に注目すべきは、セロトニンが痛みの感じ方と血管の状態に直接影響を与える点です。これが頭痛や肩こりと密接に関係している理由なのです。
セロトニンが不足すると、以下のような症状が現れやすくなります。
| 分類 | 症状 |
|---|---|
| 身体症状 | ・慢性的な頭痛(特に片頭痛) ・肩こり・首こりの悪化 ・全身の筋肉の緊張 ・疲労感が抜けない ・睡眠の質の低下 |
| 精神症状 | ・不安感やイライラ ・集中力の低下 ・やる気が出ない ・些細なことでストレスを感じやすい |
これらの症状は相互に影響し合い、悪循環を生み出してしまうのが特徴です。
 セロトニン不足による頭痛と肩こりは、以下のような悪循環を形成します。
セロトニン不足による頭痛と肩こりは、以下のような悪循環を形成します。
- セロトニン不足の開始
ストレス、不規則な生活、運動不足などでセロトニンの分泌が低下 - 血管調節機能の低下
セロトニン不足により血管の収縮・拡張のバランスが崩れ、頭痛が発生 - 筋肉緊張の増加
痛みやストレスにより首・肩周りの筋肉が過度に緊張 - 血流悪化
筋肉の緊張により血流が悪化し、さらに頭痛や肩こりが悪化 - ストレス増加
慢性的な痛みがストレスとなり、さらにセロトニンが減少
この悪循環を断ち切るには、セロトニンの分泌を促進することが重要です。
1. 規則正しい生活リズム
 朝日を浴びる:起床後すぐに日光を浴びることでセロトニンの分泌が促進
朝日を浴びる:起床後すぐに日光を浴びることでセロトニンの分泌が促進- 規則正しい睡眠:毎日同じ時間に寝起きする
- 食事時間の規則化:3食を決まった時間に摂取
2. 適度な運動
 リズム運動:ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど
リズム運動:ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど- 継続性が重要:週3回、20-30分程度から始める
- 呼吸を意識:深呼吸しながら行うとより効果的
3. セロトニンの原料となる食材を摂取
 🔸トリプトファンを含む食品
🔸トリプトファンを含む食品
- 乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)
- 大豆製品(納豆、豆腐、味噌)
- 魚類(サケ、マグロ、カツオ)
- ナッツ類(アーモンド、くるみ)
4. ストレス管理
 深呼吸・瞑想:1日5分から始める
深呼吸・瞑想:1日5分から始める- 趣味の時間:リラックスできる活動を取り入れる
- 人とのコミュニケーション:信頼できる人との会話
5. 専門的な施術
 当院では、セロトニン不足による頭痛・肩こりに対して以下のアプローチを行います。
当院では、セロトニン不足による頭痛・肩こりに対して以下のアプローチを行います。
- 筋肉の緊張緩和:手技療法による血流改善
- 体の歪みを調整:全身のバランスを整える施術
- ストレス耐性の強化:セロトニンを増やす施術
- 自律神経の調整:(セロトニンを増やす施術に含まれています)
- その他生活指導:栄養指導や運動指導なと個々の症状に合わせた改善アドバイス

頭痛や肩こりが慢性化している場合、セロトニン不足が根本的な原因の可能性があります。
薬に頼るだけでなく、生活習慣の見直しと適切な施術により、根本からの改善が期待できます。
🔸重要なポイント
🔹セロトニンは痛みの調節と血管機能に重要な役割
🔹頭痛と肩こりは相互に影響する悪循環を形成
🔹生活習慣の改善と専門的な施術の組み合わせが効果的
🔹継続的な取り組みが症状改善の鍵
関連記事のご案内
あなたやご家族の健康を守るために
大阪市西成区で姿勢や体をしっかり働けるようにしたい方へ
当院では、身体の不調を自律神経脳活性整体、体の歪み矯正や栄養指導、運動指導に加えて生活習慣や環境の改善も含めたサポートを大切にしています。
ご相談はお気軽に!